運動は健康を維持するために欠かせない要素ですが、実際にどの程度の運動が必要なのか、どんな効果が得られるのか気になる人も多いのではないでしょうか?
厚生労働省やWHO(世界保健機関)などの公的機関が発表しているデータをもとに、運動と健康の関係について詳しく解説します。
運動不足による健康リスク、適切な運動量、推奨される運動方法について知り、無理なく運動習慣を取り入れるヒントを見つけましょう。
運動不足がもたらす健康リスクとは?公的データから見る影響
1 .運動不足による死亡リスクの増加
厚生労働省の発表によると、日本人の死亡リスクの約6%は運動不足が原因とされています(厚生労働省「健康づくりのための身体活動基準2023」)。
WHO(世界保健機関)も、世界全体の年間死亡者数のうち5~6%は運動不足によるものと指摘しています。
<運動不足によって増える主な病気>
心血管疾患(心筋梗塞・脳卒中など)
糖尿病(特に2型糖尿病)
高血圧
肥満
メンタルヘルスの悪化(うつ病・不安障害)
2 .日本人の運動習慣の現状
厚生労働省のデータでは、日本人の約半数が運動不足とされています。
特に40代以降は運動量が大きく減少し、それに伴い生活習慣病のリスクが高まる傾向があります。
✅ 運動不足が深刻な年代(週150分以上の中強度の運動をしていない割合)
20代:45%
30代:50%
40代:55%(運動不足が増加)
50代:60%
60代:65%
40代からの健康維持には、意識的に運動を取り入れることが不可欠です。
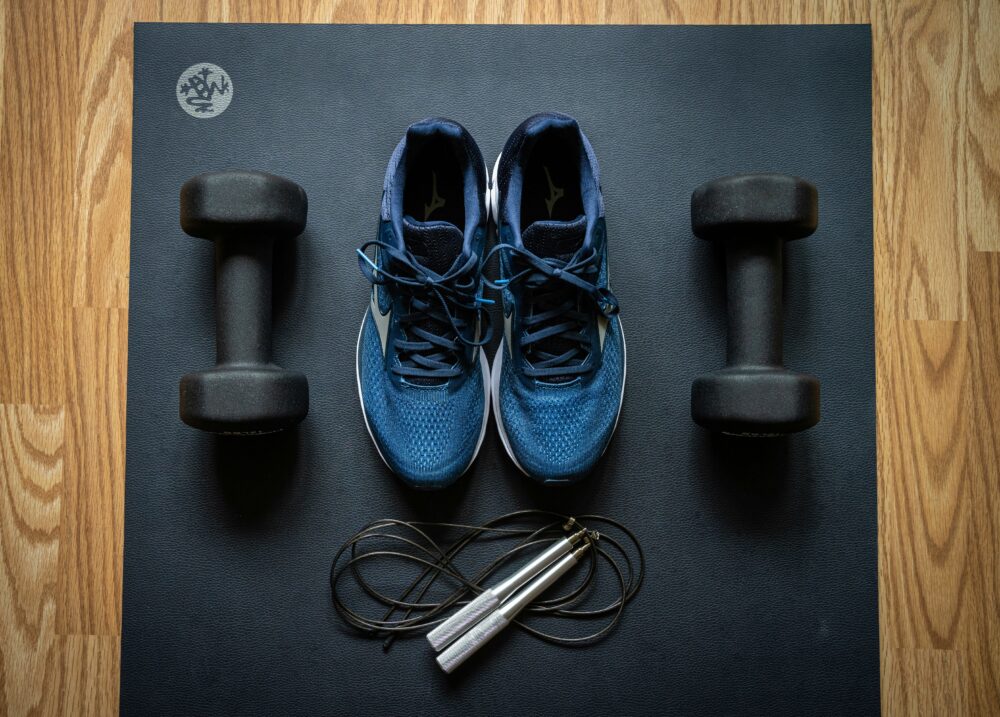
どのくらい運動すれば健康リスクを減らせるのか?
1. 厚生労働省の推奨する運動量
厚生労働省が発表している「健康づくりのための身体活動基準2023」では、週150分以上の中強度の運動が推奨されています。
この運動量は、1日20〜30分程度のウォーキングやジョギングに相当します。
2. WHOの推奨する運動ガイドライン
WHOの発表する運動ガイドラインでは、以下の2つを満たすことが理想的とされています。
✔ 中強度の運動(ウォーキング・ジョギングなど)
→ 週150~300分(1日30分×5日 or 1日20分×7日)
✔ 筋力トレーニング(スクワット・腕立て伏せなど)
→ 週2~3回
この基準を満たすと、生活習慣病の予防やストレス軽減に効果的だとされています。
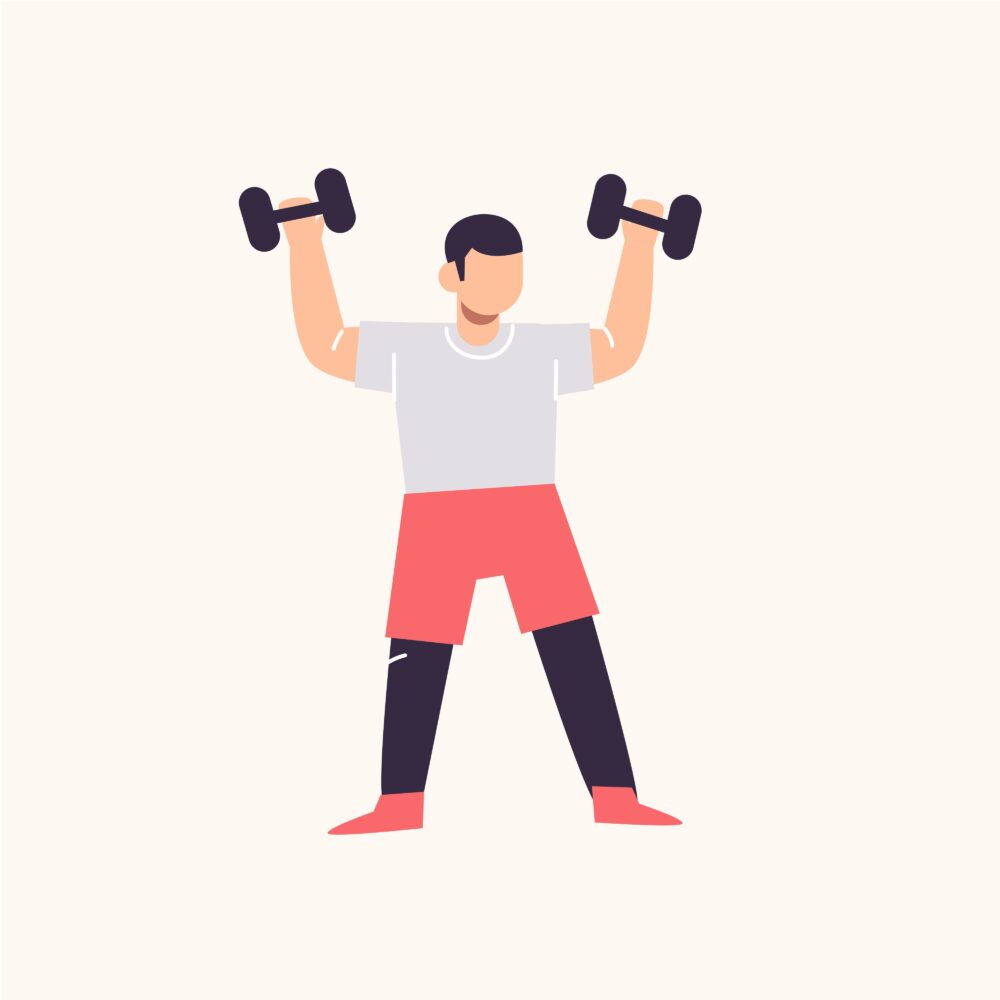
運動がもたらす具体的な健康効果
1 .生活習慣病の予防
✅ 心血管疾患リスクが40%減少(運動を習慣化すると血圧が安定)
✅ 2型糖尿病の発症リスクが50%減少(血糖値のコントロールが改善)
✅ メタボリックシンドロームの予防(内臓脂肪の減少)
2 .精神的な健康改善
✅ ストレスホルモン(コルチゾール)の減少
✅ 幸福ホルモン(セロトニン・エンドルフィン)の増加
✅ 睡眠の質の向上(運動をすることで深い眠りに入りやすくなる)
運動を習慣化すると、気分が前向きになり、メンタルヘルスにも良い影響が期待できます。
効果的な運動方法と継続のコツ
1 .まずはウォーキングから始める
初心者や忙しい人でも取り入れやすい運動として、ウォーキングが最適です。
1日20分以上歩くことで、心血管疾患のリスクを30%減らせる
通勤や買い物の際に「歩く」ことを意識すると、無理なく運動習慣がつく
2 .自宅でできる簡単な筋力トレーニング
厚生労働省の指針では、週2回以上の筋トレが推奨されています。
自宅でも簡単にできるトレーニングを取り入れると効果的です。
初心者向け筋トレメニュー(1日10分)
✔ スクワット(10回×3セット)
✔ プッシュアップ(腕立て伏せ)10回×3セット
✔ プランク(30秒×3セット)
短時間でも継続することで、基礎代謝の向上や筋力の維持が可能です。

運動を習慣化するためのポイント
1 .目標設定をシンプルにする
「毎日30分歩く」「週2回筋トレをする」など、達成しやすい目標を設定
スマホアプリで歩数や運動時間を記録すると、モチベーションが維持しやすい
2 .楽しめる運動を見つける
ジム通いが面倒なら、家で筋トレやストレッチをする
ダンスやヨガなど、自分が楽しめる運動を選ぶと継続しやすい

公的データが示す運動の重要性を理解し、無理なく実践しよう!
運動不足は生活習慣病・メンタルヘルスの悪化・死亡リスクを高める
✅ 厚生労働省とWHOは「週150分以上の有酸素運動+筋トレ」を推奨
✅ 運動を習慣化することで、生活習慣病のリスクが40〜50%低下する
✅ ウォーキング+筋トレを組み合わせると、効率よく健康を維持できる
✅ まずは「無理のない範囲」で運動を始め、継続することが大切!
今から少しずつでも運動を始めて、健康な体を維持していきましょう!

<出典>

